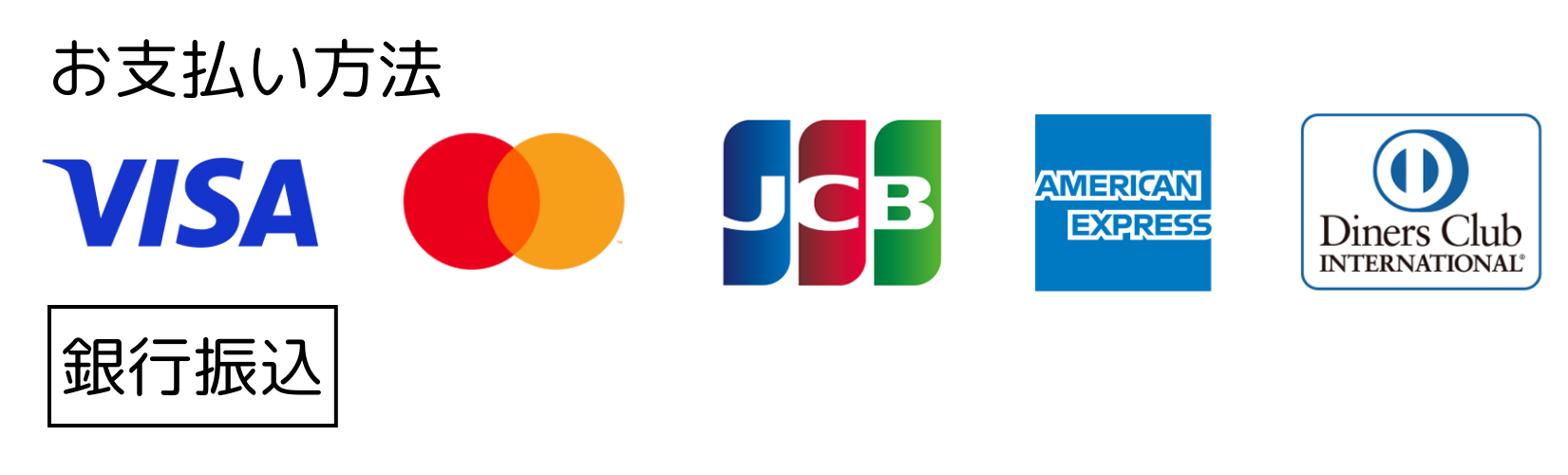アロマテラピーキーワード辞典
アロマテラピーに関するキーワード辞典です。
五十音順のカテゴリーから目的のキーワードを見つけてください。
あ行
| 圧搾法 | 柑橘系果実(オレンジ、レモン、グレープフルーツなど)の果皮を圧力でしぼり、精油を抽出する方法。フレッシュでみずみずしい香りがそのまま残るのが特徴です。ただし揮発性が高く酸化しやすいため、開封後は1年以内に使い切り、冷暗所での保管が推奨されます。 |
| アブソリュート | ジャスミンやローズなど、デリケートな花や植物から得られる香り成分を有機溶剤(ヘキサン)を使って抽出したもの。濃厚な香りが特徴で、香水の高級原料として重宝されています。 |
| アレルゲン | 精油に含まれる天然成分のうち、アレルギー反応を引き起こす可能性のある成分。代表的なものにリモネン、リナロール、シトラールなどがあり、酸化すると刺激性が高まることもあります。 |
| アロマ(アロマテラピー) | 植物の香り成分を活用した心身のバランスを整える自然療法。1930年代にフランスの化学者ルネ・モーリス・ガットフォセが「Aromathérapie」と名付け、近代アロマの礎を築きました。ストレス緩和、睡眠改善など幅広い用途で活用されています。 |
| アロマオイル | 「アロマオイル」という名前は、人工的に作られた合成香料を含む香り付きオイル全般をいいます。そのため、植物から抽出された100%天然の香りを楽しみたい場合は、「精油(エッセンシャルオイル)」と明記されたものを選ぶことが大切です。 |
| アンフルラージュ | 古典的な香り抽出法。植物の花びらを油脂に時間をかけて香りを吸着させる方法です。熱に弱い香りも損なわずに取り出せるため、現代でも一部で用いられますが、非常に手間がかかるため貴重です。 |
| オーガニック | 化学肥料や農薬を使わず、自然に配慮して植物を育てる農法。土壌や水質を守る持続可能な農業として注目されています。フロリハナの製品は、エコサート(フランス)、USDA(アメリカ)、JAS(日本)といった国際的オーガニック認証を取得しています。 |
か行
| 学名 | 植物分類における国際的に統一されたラテン語名。精油選びで混同を防ぐため、学名の確認は非常に重要です。精油選びの際、精油名で調べるより学名で調べると目的の植物に出会えます。 |
| ガスクロマトグラフィー | 精油に含まれる数百種類の成分を分析する化学的手法。フロリハナではロットごとに成分分析を実施し、品質と安全性の確保に役立てています。 |
| 希釈 | 精油をキャリアオイルなどで薄めること。肌への負担を軽減し、安全に使用できるようにします。 |
| 揮発性 | 精油は香りが揮発する速度によって、トップノート(最初の印象)、ミドルノート(香りの中心)、ベースノート(持続する深み)に分類されます。 |
| キャリアオイル(植物油) | 「ベースオイル」や「植物油」とも呼ばれ精油をお肌に運ぶ役割から「キャリアオイル」と名付けられました。マッサージやスキンケアにそのまま使用したり、精油を希釈してお肌に塗布といった用途に使われます。 |
| ケモタイプ | 同じ植物でも育つ環境や土壌によって成分構成が変わることがあり、それを区別するための分類。例えば、ローズマリーは1,8-シネオール、カンファー、ベルベノンと3種類のケモタイプが存在します。 |
| 抗菌作用 | 微生物や細菌の増殖を抑える働きを持つ成分のこと。ユーカリ、ティーツリー、ラベンダーなどの精油に含まれる1,8-シネオールやリナロールが代表的です。 |
さ行
| 酸化 | 精油が空気や光、熱にさらされることで起こる化学変化。酸化した精油は香りが変質し、肌に塗布することで肌刺激の原因になることも。開封後は冷暗所で密閉保管し、柑橘系精油は早めに使い切りましょう。 |
| ジェモセラピー | 植物の新芽や若芽、つぼみなど成長中の植物組織から抽出したエキスを使った自然療法のことです。 |
| 水蒸気蒸留 | 植物に水蒸気をあて、芳香成分を含んだ蒸気を冷却して精油を抽出する方法。多くの精油で使われる最も一般的な製法。フロリハナでは「フラッシュデタント(低温低圧蒸留)」と呼ばれる革新的な技術を用いて蒸留を行っています。これにより熱に弱い繊細な成分も壊さず抽出しています |
| 精油(エッセンシャルオイル) | 植物の花、葉、果皮、樹脂、木部などから抽出された揮発性の芳香成分を含む100%天然のオイル。心身のバランスを整えるアロマテラピーに欠かせない存在で、植物が持つ特性が凝縮されています。 |
た行
| チャイルドロック | 小さなお子様が誤って開けないように工夫された安全設計のボトルキャップ。フロリハナではすべての精油にヨーロッパ基準のチャイルドロック付きキャップを採用しています。 |
| 抽出法 | 圧搾法、水蒸気蒸留法、アブソリュート、二酸化炭素抽出などがあります。古くは油脂に花の香りを吸着させるアンフルラージュ法という抽出方法もあります。 |
| 超臨界二酸化炭素抽出 | 二酸化炭素を使用して成分を抽出する方法。抽出過程で酸素と接触しないため、酸化しやすい成分も抽出できる方法。環境にやさしい抽出方法として近年注目されています。 |
| チンキ剤 | 植物の有効成分をアルコールに抽出した液体のことです。精油とは異なり、芳香成分だけでなく、植物全体の成分も含まれるのが特徴です。エキナセアなどがあります。ドイツやフランスのホメオパシー薬局方のガイドラインに基づいて製造され、自然療法やホメオパシー、フィトテラピー(植物療法)において幅広く利用されています。 |
| トップノート | 精油を嗅いだときに最初に感じる香りの第一印象、柑橘系やペパーミントなどが代表で、揮発が早いため香りの持続は短めです。ブレンドでは第一印象を決める大切な役割を持ちます。 |
| ドロッパー | ボトルの注ぎ口に取り付けられ、一滴ずつ精油を出せるパーツ。フロリハナの精油では1滴=約0.03mlのドロッパーを採用しています。 |
な行
| 濃度 | 精油の希釈の度合いを表す目安。アロママッサージでは通常1%未満に希釈します。原液は刺激が強いため、直接肌につけるのは避けるのが基本です。 |
| 妊産婦(への使用) | 妊娠中・授乳中はホルモンバランスが変化し、精油の使用は避けるのが安全です。香りを楽しみたい場合は、低刺激なフローラルウォーターが適しています。 |
| ノーズワーク | 香りを嗅ぐことで脳や嗅覚を活性化させるトレーニング。近年は犬の嗅覚訓練としても知られています。 |
は行
| パッチテスト | 肌に初めて使用するキャリアオイルなどを使用する前に、肌の一部で刺激が出ないか確認するテスト。腕の内側に少量を塗り、24時間後の肌状態をチェックします。 |
| 光毒性 | 日光(紫外線)にあたると肌に反応がでる成分。一部の柑橘系精油(ベルガモット、グレープフルーツなど)に含まれる成分が原因で、希釈した精油を塗布後に紫外線を浴びるとシミや炎症を引き起こすことがあります。使用後は外出を避けるか、夜間に使うのが安心です。 |
| フローラルウォーター(芳香蒸留水) | 植物を水蒸気蒸留することで得られる芳香成分を含む水溶性の液体。フローラルウォーターやハーブウォーターとも呼ばれ、化粧水として使えます。香りは精油よりも穏やかで、敏感肌にもやさしいのが特徴。 |
| ペット(への使用) | 精油に含まれる成分の中には、犬や猫、その他の動物にとって有害となるものがあります。動物は人間よりも嗅覚が敏感で、肝機能の代謝も異なるため、中毒のリスクが高まります。アロマディフューザーの使用も換気を十分に行い、ペットがいる空間では避けるのが安心です。 |
| ベースノート | トップノート・ミドルノートが揮発した後に残る香りで、全体の香りに「深み」と「安定感」を与える役割を持ちます。サンダルウッド、パチュリ、ベチバーなどが代表例で、香りの持続時間は最も長く、数時間から1日近く残ることもあります。香水やアロマブレンドの“土台”になる重要な要素です。 |
| 芳香成分 | 精油に含まれる有機化合物の総称。リナロール、シトラール、1,8-シネオールなどが代表例で、それぞれ香りや作用が異なります。フロリハナではロットごとの成分分析を行っています。成分分析は精油の品質や安全性を確認する重要な指標です。 |
| 芳香浴 | 精油を空気中に拡散させ、その香りを楽しむ方法。アロマディフューザー、アロマランプ、マグカップにお湯を注いで数滴垂らす簡易的な方法などがあります。リラックス、リフレッシュなど気分転換したいときに活用できます。 |
ま行
| マセレーションオイル(浸出油) | 植物油にハーブや花を長時間漬け込み、有効成分や香りを抽出したオイル。マリーゴールド(カレンデュラ)のマセレーションオイルは、敏感肌やベビーケアにも使用される人気のアイテムです。 |
| ミドルノート | トップノートの後に感じられる「香りの中心」を担う部分で、ラベンダー、ゼラニウムなどが代表例で、揮発速度は中程度。ブレンドの調和役ともいわれます。 |
や行
| 薬機法 | 化粧品や医薬品などに関する品質、有効性、安全性に関する日本の法律。 |
| 有機栽培 | オーガニックの項目をご覧ください。《オーガニック》 |
ら行
| ロットナンバー | 製造管理とトレーサビリティのために付けられる製品番号。全ての商品にロットナンバーを付与しています。 |
わ行
| ワシントン条約 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の略称。精油では、採取や輸出入が規制されている植物もあります。 |
| 和精油 | 日本国内の植物を原料とし、国内で抽出された精油。ユズ、ヒノキなど、日本ならではの植物の香りが楽しめます。和の香りは海外でも人気が高いです。 |